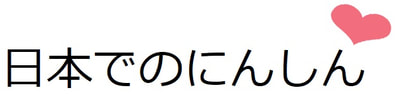日本で出産するのにいくらかかりますか?
妊娠・出産にかかる費用と補助制度
日本では、妊娠・出産は病気ではないので、公的な健康保険が使えません。(つわりがひどい時の治療や帝王切開の手術費などには保険が使えます。)手続きをしないと、妊娠・出産の費用は、基本的に全部自分で払わなければなりません。
ただし、妊娠が分かった後に、住民票のある市町村の子育て支援課に届けると、「母子健康手帳」と助成クーポン(妊婦検診補助券)がもらえます。このクーポンで、自分で払うお金は少なくなります。補助の内容と金額は各自治体によって異なります。住民届をしていなかったり、オーバーステイでももらえる場合があります。また、赤ちゃんが生まれる前や生まれた後の準備、日用品(オムツやミルク代など)の費用もかかります。
ただし、妊娠が分かった後に、住民票のある市町村の子育て支援課に届けると、「母子健康手帳」と助成クーポン(妊婦検診補助券)がもらえます。このクーポンで、自分で払うお金は少なくなります。補助の内容と金額は各自治体によって異なります。住民届をしていなかったり、オーバーステイでももらえる場合があります。また、赤ちゃんが生まれる前や生まれた後の準備、日用品(オムツやミルク代など)の費用もかかります。
1)妊婦健診の費用
妊娠検査(初めての妊婦検診):
5,000円~10,000円
※病院や検査の内容によって変わります。
2回目以降の妊婦検診:
5,000円~8,000円程度。
※補助券を使うと、実際に支払う金額は2000円〜3000円程度になることが多いです。
血液検査がある場合は、10,000円~15,000円程度。
※補助券が使える検査と補助券が使えない検査があります。
【妊婦健診補助の手続き】
【妊婦検診補助券を使った妊婦検診の回数:13~14回】
妊娠初期〜23週 4週間に1回
24週〜35週 2週間に1回
36週以降 1週間に1回
5,000円~10,000円
※病院や検査の内容によって変わります。
2回目以降の妊婦検診:
5,000円~8,000円程度。
※補助券を使うと、実際に支払う金額は2000円〜3000円程度になることが多いです。
血液検査がある場合は、10,000円~15,000円程度。
※補助券が使える検査と補助券が使えない検査があります。
【妊婦健診補助の手続き】
- 産婦人科で、妊娠の診断をしてもらう
※一番初めの診察は、全額自己負担です。 - 住民票のある自治体の窓口で、「母子手帳」と「妊婦検診補助券」をもらう。
※一般的には、産婦人科の医師から手続きのための書類(妊娠届出書)をもらってから自治体の窓口に手続きに行きます。
(産婦人科からの書類がなくても母子手帳等をくれる自治体もあります。)2回目からの検査に妊婦検診補助券を使いたい場合は、医師に手続きの時期を相談しましょう。
※母子手帳等をもらうために必要な書類は自治体によって違います。熊本市は、産婦人科からの「妊娠届出書」が必要です。
【妊婦検診補助券を使った妊婦検診の回数:13~14回】
妊娠初期〜23週 4週間に1回
24週〜35週 2週間に1回
36週以降 1週間に1回
2)出産準備のための費用
産まれて来る赤ちゃんのために、オムツやミルクなどの準備も必要です。手続きをすると自治体からオムツやミルクを買うための補助(約5万円のクーポンや現金)がもらえます。
※補助の内容は自治体によってちがいます。
【手続き】
母子手帳をもらうための手続きをしたら、自治体から補助の案内の手紙が届きます。手続きの方法は、その案内の手紙に書いてあります。電子申請ができる自治体もあります。詳しくは、母子手帳をもらうための手続きをする時に、自治体の係の人に聞いてください。
※補助の内容は自治体によってちがいます。
【手続き】
母子手帳をもらうための手続きをしたら、自治体から補助の案内の手紙が届きます。手続きの方法は、その案内の手紙に書いてあります。電子申請ができる自治体もあります。詳しくは、母子手帳をもらうための手続きをする時に、自治体の係の人に聞いてください。
3)出産にかかる費用
自然分娩の場合:
自然分娩とは、自然の流れに沿った出産のことです。原則として健康保険が使えないので、全て自費となります。費用は、400,000円~800,000円程度かかります。また、このほかに入院費がかかります。
帝王切開分娩の場合:
帝王切開分娩とは、妊婦のお腹をメスで切り、お腹から赤ちゃんを取り出す出産方法です。帝王切開分娩は、健康保険が使えますが、200,000円程度かかります。また、このほかに入院費用がかかります。
自然分娩とは、自然の流れに沿った出産のことです。原則として健康保険が使えないので、全て自費となります。費用は、400,000円~800,000円程度かかります。また、このほかに入院費がかかります。
帝王切開分娩の場合:
帝王切開分娩とは、妊婦のお腹をメスで切り、お腹から赤ちゃんを取り出す出産方法です。帝王切開分娩は、健康保険が使えますが、200,000円程度かかります。また、このほかに入院費用がかかります。
出産費用がない場合(入院助産制度)
出産の時に経済的な理由で入院することができない妊婦が、安い費用で入院助産を受けることができる制度があります。
健康保険に未加入の場合や、オーバーステイの場合でも受けることができます。住んでいる自治体の子育て支援課で相談できます。
健康保険に未加入の場合や、オーバーステイの場合でも受けることができます。住んでいる自治体の子育て支援課で相談できます。
出産・育児で受け取ることができるお金
技能実習生等の外国人も出産育児一時金などの出産や育児にかかわる制度を利用できます。在留資格は関係ありません。だだし、それぞれの条件を満たしている必要があります。
出産育児一時金
出産は病気ではないので健康保険は使えません。しかし、出産費用は、健康保険から補助が出ます。また、健康保険に入っていなくても、国民健康保険に入っていれば出産育児一時金がもらえます。
対象:
健康保険や国民健康保険に入っている人が出産した時に出産育児一時金がもらえます。健康保険に入っている人の被扶養者(健康保険に入っている人と一緒に住み、お金や生活の面倒を見てもらっている家族)が出産した時も一時金がもらえます。妊娠4か月(85日)経っていれば、流産や死産の時も一時金がもらえます。
日本で出産する場合だけではなく、健康保険や国民健康保険に入っている時に出身国に一時帰国して出産した場合も出産育児一金をもらえます。
また、退職時に健康保険に継続して一年以上入っていた場合、退職日からから6カ月以内に出産したら、出産育児一時金をもらえます。退職をして出身国に帰国した後に出産しても一時金がもらえます。ただし、国民健康保険の場合は、在留期間を過ぎてから出身国に帰国して出産した場合は一時金はもらえません
金額:
子ども一人につき500,000円。
手続き:
日本で出産する場合には、出産で病院に行くとき、受付で申し込みます。多くの病院では「直接支払い制度」という、医療保険者から病院へ直接お金が支払われる制度が使えます。なので、出産にかかったお金のうち自己負担分(500,000円より多くかかった金額)だけ支払えばいいです。出産でかかったお金が500,000円より少ない場合は、差額をもらうことができます。
社会保険に入っている人が出身国で出産する場合に必要な書類:「出産育児一時金支給申請書」、母子手帳のコピー、出生証明書(死産や流産の場合は死産証明書)とその日本語訳 (出産一時金支給申請書には、日本国内の口座番号の記入が必要です。)
国民健康保険に入っている人が出身国に一時帰国して出産する場合には、日本に帰ってきた後に以下の書類の提出が必要です:「出産育児一時金支給申請書」とパスポート、出生証明書(死産や流産の場合は死産証明書)とその日本語訳、保険証、通帳等、母子健康手帳
対象:
健康保険や国民健康保険に入っている人が出産した時に出産育児一時金がもらえます。健康保険に入っている人の被扶養者(健康保険に入っている人と一緒に住み、お金や生活の面倒を見てもらっている家族)が出産した時も一時金がもらえます。妊娠4か月(85日)経っていれば、流産や死産の時も一時金がもらえます。
日本で出産する場合だけではなく、健康保険や国民健康保険に入っている時に出身国に一時帰国して出産した場合も出産育児一金をもらえます。
また、退職時に健康保険に継続して一年以上入っていた場合、退職日からから6カ月以内に出産したら、出産育児一時金をもらえます。退職をして出身国に帰国した後に出産しても一時金がもらえます。ただし、国民健康保険の場合は、在留期間を過ぎてから出身国に帰国して出産した場合は一時金はもらえません
金額:
子ども一人につき500,000円。
手続き:
日本で出産する場合には、出産で病院に行くとき、受付で申し込みます。多くの病院では「直接支払い制度」という、医療保険者から病院へ直接お金が支払われる制度が使えます。なので、出産にかかったお金のうち自己負担分(500,000円より多くかかった金額)だけ支払えばいいです。出産でかかったお金が500,000円より少ない場合は、差額をもらうことができます。
社会保険に入っている人が出身国で出産する場合に必要な書類:「出産育児一時金支給申請書」、母子手帳のコピー、出生証明書(死産や流産の場合は死産証明書)とその日本語訳 (出産一時金支給申請書には、日本国内の口座番号の記入が必要です。)
国民健康保険に入っている人が出身国に一時帰国して出産する場合には、日本に帰ってきた後に以下の書類の提出が必要です:「出産育児一時金支給申請書」とパスポート、出生証明書(死産や流産の場合は死産証明書)とその日本語訳、保険証、通帳等、母子健康手帳
出産手当金
仕事をしていて健康保険に入っている場合、出産のために仕事を休むと、「出産手当金」がもらえます。
対象:
健康保険に入っていて、出産のために仕事を休んでいる間会社から給料が支払われなかった人は出産手当金をもらえます。ただし、出産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、産後56日までの期間が支給の対象となります。国民健康保険に入っている人は出産手当金をもらえません。
退職時に健康保険に継続して一年以上入っていて、退職日の翌日までに出産手当金をもらっていた場合は、退職しても引き続き出産手当金をもらえます。日本を離れても出産手当金をもらえます。
金額:
標準報酬日額(休む前の一日分の給料)の3分の2の金額を、休んだ日数分もらえます。
手続き:
産休(出産休暇)に入る前に、会社に申請します。会社が申請をしないこともあります。その時は健康保険組合に直接申請をします。
対象:
健康保険に入っていて、出産のために仕事を休んでいる間会社から給料が支払われなかった人は出産手当金をもらえます。ただし、出産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、産後56日までの期間が支給の対象となります。国民健康保険に入っている人は出産手当金をもらえません。
退職時に健康保険に継続して一年以上入っていて、退職日の翌日までに出産手当金をもらっていた場合は、退職しても引き続き出産手当金をもらえます。日本を離れても出産手当金をもらえます。
金額:
標準報酬日額(休む前の一日分の給料)の3分の2の金額を、休んだ日数分もらえます。
手続き:
産休(出産休暇)に入る前に、会社に申請します。会社が申請をしないこともあります。その時は健康保険組合に直接申請をします。
育児休業給付金
1歳未満の子どもを育てるために職場の育児休業制度を利用して仕事を休んでいる間、「育児休業給付金」をもらえます。もらえる金額は、休業前の給料によって異なります。
対象:
雇用保険に入っていて、職場の育児休業制度を利用して仕事を休んでいる人は給付金をもらえます。子どもが1歳になるまで給付金がもらえます。
技能実習生など労働契約の期間が決まっている人も、出産した子どもが1歳6カ月になるまで雇用契約が継続するのであれば育児休業が取れます。出産した子どもが1歳6カ月になる前に雇用契約が終わる場合は、育児休業は取れません。(だだし、雇用契約が更新される予定であれば育児休業が取れます。)また、会社によっては、入社して1年未満の人には育児休業を取らせないという労使協定(会社とその会社の労働者たちの契約)があります。入社して1年未満の人は、育児休業が取れるかを会社に確認する必要があります。
金額:
育児休業給付金をもらう日数が180日までは、休業前の給料の67%の金額がもらえます。その後は休業前の給料の50%の金額がもらえます。給付金は2カ月に1回、2か月分が支払われます。
手続き:
会社から、ハローワークに申し込みをしてもらいます。会社が申し込みをしてくれない場合は、自分でハローワークに行って申し込みをします。
対象:
雇用保険に入っていて、職場の育児休業制度を利用して仕事を休んでいる人は給付金をもらえます。子どもが1歳になるまで給付金がもらえます。
技能実習生など労働契約の期間が決まっている人も、出産した子どもが1歳6カ月になるまで雇用契約が継続するのであれば育児休業が取れます。出産した子どもが1歳6カ月になる前に雇用契約が終わる場合は、育児休業は取れません。(だだし、雇用契約が更新される予定であれば育児休業が取れます。)また、会社によっては、入社して1年未満の人には育児休業を取らせないという労使協定(会社とその会社の労働者たちの契約)があります。入社して1年未満の人は、育児休業が取れるかを会社に確認する必要があります。
金額:
育児休業給付金をもらう日数が180日までは、休業前の給料の67%の金額がもらえます。その後は休業前の給料の50%の金額がもらえます。給付金は2カ月に1回、2か月分が支払われます。
手続き:
会社から、ハローワークに申し込みをしてもらいます。会社が申し込みをしてくれない場合は、自分でハローワークに行って申し込みをします。
傷病手当金
傷病手当金は、病気やケガで働くことができない期間中にもらえるお金です。妊娠していて体調が悪くて仕事ができない場合も傷病手当金がもらえる場合があります。
対象:
傷病手当金は健康保険の制度です。国民健康保険に入っている人は傷病手当がありません。
傷病手当金がもらえる条件は、社会保険組合によって違います。しかし一般的な条件は以下です。
金額:
連続して会社を休んだ3日間の翌日から最長1年6カ月の間、傷病手当がもらえます。月収の3分の2がもらえます。仕事を休んでいる間に会社から給料が出ていても、傷病手当金の金額よりも低ければ、その差額がもらえます。
手続き:
会社と医者に「傷病手当金支給申請書」を記入してもらいます。(医者の診断書は意見書の代わりにはなりません。)そして保険協会に申請します。
対象:
傷病手当金は健康保険の制度です。国民健康保険に入っている人は傷病手当がありません。
傷病手当金がもらえる条件は、社会保険組合によって違います。しかし一般的な条件は以下です。
- 妊娠で体調が悪くて仕事ができない
- 連続する3日間を含む4日以上、仕事ができない
- 仕事をしていない間は給料が出ない
金額:
連続して会社を休んだ3日間の翌日から最長1年6カ月の間、傷病手当がもらえます。月収の3分の2がもらえます。仕事を休んでいる間に会社から給料が出ていても、傷病手当金の金額よりも低ければ、その差額がもらえます。
手続き:
会社と医者に「傷病手当金支給申請書」を記入してもらいます。(医者の診断書は意見書の代わりにはなりません。)そして保険協会に申請します。
乳幼児医療費助成
産まれた子どもが病院で診察や治療を受けた時に、その費用の一部または全額を住んでいる自治体(住民票のある市町村)が助成してくれる制度です。
対象:
子どもが健康保険か国民健康保険に入っていることが条件です。
子どもが何歳になるまで「乳幼児医療費助成」が使えるか、どのような時に使えるかは、住んでいる自治体によって違います。住んでいる自治体に相談して、確認しましょう。
金額:
金額も、住んでいる自治体によって違います。かかった医療費を全部支払わなくていい場合や、一部を支払わなければいけないときもあります。
手続き:
子どもが生まれたら、住んでいる市町村の子育て支援課に申し込んで、「乳幼児医療証」をもらいます。子どもが病院に行く時、病院で保険証と一緒に「乳幼児医療証」を見せます。子どもの一カ月健診から「乳幼児医療費助成」が使えるので、間に合うように申し込みをしましょう。
対象:
子どもが健康保険か国民健康保険に入っていることが条件です。
子どもが何歳になるまで「乳幼児医療費助成」が使えるか、どのような時に使えるかは、住んでいる自治体によって違います。住んでいる自治体に相談して、確認しましょう。
金額:
金額も、住んでいる自治体によって違います。かかった医療費を全部支払わなくていい場合や、一部を支払わなければいけないときもあります。
手続き:
子どもが生まれたら、住んでいる市町村の子育て支援課に申し込んで、「乳幼児医療証」をもらいます。子どもが病院に行く時、病院で保険証と一緒に「乳幼児医療証」を見せます。子どもの一カ月健診から「乳幼児医療費助成」が使えるので、間に合うように申し込みをしましょう。
児童手当
産まれた子どもが中学校を卒業するまで、子ども1人につき月額5,000円~15,000円がもらえます。(子供の年齢、所得によってもらえる金額がちがいます。所得金額が多い人は、手当をもらえない場合もあります。)子どもは、原則として日本に住んでいることが条件です。
対象:
15歳まで(中学校を卒業するまで)の子どもを育てる保護者(父母など)。
金額:
収入が多い人は、子どもの年齢に関係なく月額5,000円もらえます。もっと所得が多い人は、手当をもらえない場合もあります。
お金は、毎年6月、10月、2月に4か月分がまとめてもらえます。
手続き:
子どもを出産してから15日以内に、住んでいる自治体(住民票のある市町村)に申請します。遅れて申請したら、過ぎた月分の児童手当はもらえなくなります。
対象:
15歳まで(中学校を卒業するまで)の子どもを育てる保護者(父母など)。
金額:
- 0歳~3歳未満:月額15,000円
- 3歳から小学校卒業まで(1人目・2人目):月額10,000円
- 3歳から小学校卒業まで(3人目以降):月額15,000円
- 中学生:月額10,000円
収入が多い人は、子どもの年齢に関係なく月額5,000円もらえます。もっと所得が多い人は、手当をもらえない場合もあります。
お金は、毎年6月、10月、2月に4か月分がまとめてもらえます。
手続き:
子どもを出産してから15日以内に、住んでいる自治体(住民票のある市町村)に申請します。遅れて申請したら、過ぎた月分の児童手当はもらえなくなります。
児童扶養手当
ひとり親家庭や、お父さんやお母さんに重度の障害がある場合、所得によって、約10,000円~約40,000円もらえます。子どもは、原則として日本に住んでいることが条件です。
対象:
ひとり親家庭や、お父さんやお母さんに重度の障害がある場合などで、18歳まで(18歳になった日の後の最初の3月31日まで)の子どもを育てている父または母、もしくは父母にかわってその子どもを育てている人。
金額:
金額は、子どもの人数や所得によって違います。お金は、2カ月に一回、2か月分がまとめてもらえます。
手続き:
住んでいる自治体(住民票のある市町村)の子育て支援課に申し込みをします。
対象:
ひとり親家庭や、お父さんやお母さんに重度の障害がある場合などで、18歳まで(18歳になった日の後の最初の3月31日まで)の子どもを育てている父または母、もしくは父母にかわってその子どもを育てている人。
金額:
金額は、子どもの人数や所得によって違います。お金は、2カ月に一回、2か月分がまとめてもらえます。
手続き:
住んでいる自治体(住民票のある市町村)の子育て支援課に申し込みをします。
産後の赤ちゃんの日用品などに使えるお金の助成
出産後は、赤ちゃんのお世話のための日用品や消耗品がたくさん必要です。そのためのお金の助成があります。
対象:
出生届を出した人で、自治体の係の人との産後の面談を受けた人
金額:
5万円相当のクーポンまたは現金
手続き:
面談を受けた後、係の人から手続きの説明があります。詳しくは、面談をしてくれた係の人に確認してください。
対象:
出生届を出した人で、自治体の係の人との産後の面談を受けた人
金額:
5万円相当のクーポンまたは現金
手続き:
面談を受けた後、係の人から手続きの説明があります。詳しくは、面談をしてくれた係の人に確認してください。