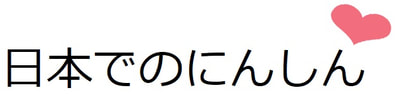産みたくないときは、どうすればいいですか?
日本では、妊娠22週未満(21週6日)まで人工妊娠中絶ができます。
中絶ができる条件
日本では、法律で中絶ができる条件が決まっています。中絶ができる条件は以下です。
中絶するためには、原則として配偶者や妊娠した相手の同意が必要です。相手が分からない時や、相手が意思表示をする事ができない時、相手が亡くなった場合には、相手の同意がなくても中絶ができます。
中絶手術
妊娠12週未満の場合は「吸引法」または「搔爬法」と言われる手術です。事前に診察を受けていれば、当日から1泊2日の処置です。出血が続くと、入院が長引くことがあります。
妊娠12週から22週未満の場合、子宮収縮剤で人工的に陣痛をおこして流産させる方法です。体への負担が大きいので数日入院が必要です。
手術には麻酔を使います。手術中、万一の場合の処置について同意を求めることができる「付き添い」や、電話ですぐ連絡がとれる緊急連絡先の提示を求められます。日本語がわかる人が望ましいです。
中絶の費用
健康保険がきかないので、自費診療です。妊娠何週目かで費用が異なります。10万円から30万円ほどかかります。妊娠後4ケ月(85日)以上の人工妊娠中絶は、出産として扱われます。健康保険に入っていれば「出産育児一時金」を受けられます。医療機関によって受け取る方法が異なるので、病院で確認しましょう。
中絶薬
2023年4月から日本でも経口中絶薬メフィーゴパックが承認されました。一つ目の薬(ミフェプリストン)を飲んだ後、36~48時間後に二つ目の薬(ミソプロストール)を飲むことで、妊娠中絶ができます。腹痛や出血等の副作用もあります。中絶薬を飲んだ後は、中絶が確認できるまで病院で待たなければいけません。中絶薬は、妊娠9週0日までが対象です。それ以降は、中絶薬は使えません。
中絶ができる条件
日本では、法律で中絶ができる条件が決まっています。中絶ができる条件は以下です。
- 母体の健康上または経済上の理由で、妊娠の継続または分娩が困難な場合
- 暴行もしくは脅迫によって、性交を抵抗・拒絶することができなかった場合
中絶するためには、原則として配偶者や妊娠した相手の同意が必要です。相手が分からない時や、相手が意思表示をする事ができない時、相手が亡くなった場合には、相手の同意がなくても中絶ができます。
中絶手術
妊娠12週未満の場合は「吸引法」または「搔爬法」と言われる手術です。事前に診察を受けていれば、当日から1泊2日の処置です。出血が続くと、入院が長引くことがあります。
妊娠12週から22週未満の場合、子宮収縮剤で人工的に陣痛をおこして流産させる方法です。体への負担が大きいので数日入院が必要です。
手術には麻酔を使います。手術中、万一の場合の処置について同意を求めることができる「付き添い」や、電話ですぐ連絡がとれる緊急連絡先の提示を求められます。日本語がわかる人が望ましいです。
中絶の費用
健康保険がきかないので、自費診療です。妊娠何週目かで費用が異なります。10万円から30万円ほどかかります。妊娠後4ケ月(85日)以上の人工妊娠中絶は、出産として扱われます。健康保険に入っていれば「出産育児一時金」を受けられます。医療機関によって受け取る方法が異なるので、病院で確認しましょう。
中絶薬
2023年4月から日本でも経口中絶薬メフィーゴパックが承認されました。一つ目の薬(ミフェプリストン)を飲んだ後、36~48時間後に二つ目の薬(ミソプロストール)を飲むことで、妊娠中絶ができます。腹痛や出血等の副作用もあります。中絶薬を飲んだ後は、中絶が確認できるまで病院で待たなければいけません。中絶薬は、妊娠9週0日までが対象です。それ以降は、中絶薬は使えません。
中絶薬を自分で飲むのは絶対にやめましょう
医師の監督をうけないで、自分で薬を飲んで中絶するのは危険です。不正出血や不完全な中絶になる可能性があります。
出身国から送ってもらったり、自分で持ち込んで薬を飲んで中絶すると、「堕胎罪」(刑法第212条 1年以下の懲役に処す)で、罰せられる場合もあります。
妊娠がわかったら、どんな場合でも、まず医師に相談しましょう。
ただし、病院によっては日本語の通訳がいないと受診を断る病院もあります。病院で受診や中絶を断られた場合は相談してください。
出身国から送ってもらったり、自分で持ち込んで薬を飲んで中絶すると、「堕胎罪」(刑法第212条 1年以下の懲役に処す)で、罰せられる場合もあります。
妊娠がわかったら、どんな場合でも、まず医師に相談しましょう。
ただし、病院によっては日本語の通訳がいないと受診を断る病院もあります。病院で受診や中絶を断られた場合は相談してください。